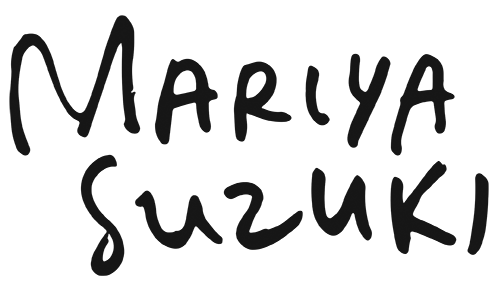「流されんなよ!甘えんなよ!元気だせよ!」
たった3行の、宛名も差出人も書いてない手紙が、しまってあった荷物の奥の方からふと出てきたのは、訃報のほんの1週間後くらいのことやった。こんなとこにこんなんしまってたんや。しまってあった年数が嘘みたいに、やけに白くてピンとしてる。
こうゆうものって、絶妙なタイミングで出てくる。誰がわたし宛にこれを書いたのかを知ってるのはふたりしかいなくて、一人はわたしで、もうひとりはいなくなってしまった。
昨年は心の調子が良くなくて、なにもかもどうでもいいような気がしてた。急な下り坂を転がっていって、自分の無力さとか存在の無意味さに押しつぶされそうになってしんどかった。昨年の記憶がほとんどない。それでも、宇宙は諦めないでいてくれたようで、わたしの周りで起こる小さな奇跡の数々に救われて、少しずつ穴の中から這い上がることができた。新しい出会いたち。前から知ってた人たちからのやさしさ。彼らはこんなわたしを大事にしてくれた。真摯に向き合ってくれた。
絵を、また描けるようになってきた。個展を開きたい気持ちが湧いてきた。それまでの自分を思うと、すごく不思議やった。濁った重たい空気の層のうえにある、軽い空気の存在を知るような感覚やった。
少しずつ上を向くことができるようになったときの訃報は辛かった。
信じたくなかった。
ルームメイトと、本人との共通の友だち以外、誰にも話すことができひんかった。
幸いなことに、わたしは訃報への免疫が低い。歳を重ねるごとに慣れてくるのかもしれないと思うとすごく悲しくなる。
それと同時に、身近な、若すぎるそれと突然すぎるそれにはいつになっても慣れることはない気もする。周りで人が死んでいくことは辛い。知らない人が死んでいくのも辛い。無惨な死を強いられる人のことを考えるとほんまにやりきれへん。
わたしにはどうすることもできひん。
手紙は、死んだように生きてたわたしのことを叱ってるようにも見えた。そんなふうに生きている自分に罪悪感を感じて、また自己嫌悪に陥る。
でも手紙はやさしくしか見えなかった。
だからってなにもせずにいたら、それこそ無意味や。自分が、自分の存在を無意味にしてるんや。わたしには、わたしにできることしかできひん。できひんことができひんからって、できることにまで意味がないと勘違いして、それすらもしなくなってた。
手紙はもっと積極的に生きろってわたしに言ってる気がした。何やってんねん!って。20年も前の手紙が、今のわたしにそう言う。
先日、「Harold & Maude」が目黒シネマで上映してるのをたまたま知って慌てて観に行った。何年ぶりやろう。その中でMaudeが言ってた。
“A lot of people enjoy being dead. But they are not dead, really. They're just backing away from life. Reach out. Take a chance. Get hurt even. But play as well as you can. Go team, go! Give me an L. Give me an I. Give me a V. Give me an E. L-I-V-E. LIVE!”